他の問題・解説はこちらへ→ 一 覧
問1 医薬品の本質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり、その有用性が認められたものである。
b 人体に対して直接使用されない医薬品は、人の健康に影響を与えることはない。
c 一般用医薬品は、使用に際して、保健衛生上のリスクを伴わないものである。
d 購入者が、一般用医薬品を適切に選択し、適正に使用するためには、その販売に専門家が関与し、専門用語を分かりやすい表現で伝えるなどの適切な情報提供を行うことが不可欠である。
a b c d
1 正 正 正 誤
2 正 誤 正 正
3 正 誤 誤 正
4 誤 誤 正 誤
5 誤 正 誤 正
問1
a.正
b.誤:例えば、殺菌消毒薬は手指や皮膚の表面、創傷部に適用されるもののほか、器具等の殺菌・消毒を目的とする製品もあり、公衆衛生を通じて人の健康に影響を与えます。
c.誤:一般用医薬品も、使用方法を誤ると健康被害を生じることがあり、保健衛生上のリスクを伴います。
d.正
正答:3
問2 医薬品の本質に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品医療機器等法では、健康被害の発生の可能性があるときに限り、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売してはならない旨を定めている。
b 一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法(平成6年法律第85号)の対象である。
c 一般用医薬品には、製品に添付されている文書(添付文書)や製品表示に、効能効果等の購入者等が適切に使用するために必要な情報が記載されている。
d 一般用医薬品の販売に従事する専門家は、市販後の有効性、安全性に関する情報の把握に努める必要はない。
1( a,b ) 2( a,c ) 3( a,d ) 4( b,c ) 5( b,d )
問2
a.誤:医薬品医療機器等法では、健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売等してはならない旨を定めています。
b.正
c.正
d.誤:一般用医薬品の販売に従事する専門家は、医薬品の適正な使用を確保するため、製造販売業者等から提供される情報の活用や、必要な情報の収集、検討、利用を行うことに努めなければならないとされています。
正答:4
問3 医薬品のリスク評価に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品に対しては、製造販売後安全管理の基準として、Good Post-marketing Study Practice(GPSP)が制定されている。
b 50%致死量(LD50)は、動物実験により求められ、薬物の毒性の指標として用いられる。
c 新規に開発される医薬品のリスク評価は、医薬品開発の国際的な標準化(ハーモナイゼーション)制定の流れのなかで、個々の医薬品の用量-反応関係に基づいて、医薬品の安全性に関する非臨床試験の基準であるGood Laboratory Practice(GLP)の他に、医薬品毒性試験法ガイドラインに沿って、毒性試験が厳格に実施されている。
d 少量の医薬品の投与でも、長期投与されれば慢性的な毒性を発現する場合がある。
a b c d
1 誤 正 正 正
2 正 誤 誤 正
3 正 誤 正 誤
4 誤 正 誤 誤
5 誤 誤 正 正
問3
a.誤:医薬品に対しては、製造販売後の調査及び試験の実施の基準としてGood Post-marketing Study Practice(GPSP)が、そして製造販売後安全管理の基準としてGood Vigilance Practice(GVP)が制定されています。
b.正
c.正
d.正
正答:1
問4 いわゆる健康食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 健康食品は、錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売されることはない。
b 「機能性表示食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。
c 「栄養機能食品」は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分の補給を目的としたものである。
d 健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じることがある。
a b c d
1 正 誤 誤 正
2 誤 誤 正 正
3 正 正 正 誤
4 誤 誤 正 誤
5 誤 正 誤 正
問4
a.誤:錠剤やカプセル剤等の形状の加工食品として販売される健康食品もあります。
b.誤:「特定保健用食品」の説明。「機能性表示食品」は、特定の保健の目的が期待できる機能性を表示できますが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
c.正
d.正
正答:2
問5 セルフメディケーション等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品のうち、医師等の診断、処方箋に基づき使用されていた医療用医薬品を薬局や店舗販売業などで購入できるように転用した医薬品をスイッチOTC医薬品という。
b 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、全ての一般用医薬品がセルフメディケーション税制の対象となっている。
c 世界保健機関(WHO)によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされている。
a b c
1 正 正 正
2 正 誤 正
3 正 正 誤
4 誤 誤 正
5 誤 正 誤
問5
a.正
b.誤:セルフメディケーション税制の対象は、スイッチOTC医薬品に加え、腰痛や肩こり、風邪やアレルギーの諸症状に対応する一般用医薬品に拡大されましたが、全ての一般用医薬品が対象となっているわけではありません。
c.正
正答:2
問6 医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を使用した場合には、期待される有益な反応(主作用)以外の反応が現れることがあり、特段の不都合を生じないものであれば、通常、副作用として取り扱われることはないが、好ましくないものについては一般に副作用という。
b アレルギーは、医薬品の薬理作用等とは関係なく起こり得るものであり、内服薬によって引き起こされることがあるが、外用薬で引き起こされることはない。
c アレルギー症状のうち、血管性浮腫は蕁麻疹と同様に痒みを生じることが多い。
d 医薬品の中には、鶏卵や牛乳等を原材料として作られているものがあるため、それらに対するアレルギーがある人では使用を避けなければならない場合がある。
a b c d
1 正 正 正 正
2 正 正 誤 誤
3 正 誤 誤 正
4 誤 誤 正 誤
5 誤 誤 誤 正
問6
a.正
b.誤:アレルギーは医薬品の薬理作用とは関係なく起こり得るもので、内服薬だけでなく外用薬等でも引き起こされることがあります。
c.誤:アレルギー症状として蕁麻疹や湿疹、かぶれ等の皮膚症状、血管性浮腫などの腫れが生じることがあります。蕁麻疹は強い痒みを伴いますが、それ以外のアレルギー症状では痒みがないか、あってもわずかであることが多いとされています。血管性浮腫が蕁麻疹と同様に強い痒みを伴うとは明記されていません。
d.正
正答:3
問7 医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を使用する人が副作用を初期段階で認識することにより、副作用の種類に応じて速やかに適切に処置し、又は対応し、重篤化の回避が図られることが重要となる。
b 一般の生活者が医療用医薬品の使用を自己判断で中止すると、副作用による不都合よりも重大な治療上の問題を生じることがあるため、診療を行った医師(又は歯科医師)、調剤した薬剤師に確認する必要がある。
c 副作用は容易に異変を自覚できるものばかりであり、血液や内臓機能への影響等は直ちに明確な自覚症状として現れる。
a b c
1 正 正 誤
2 正 誤 正
3 誤 正 正
4 誤 誤 正
5 正 誤 誤
問7
a.正
b.正
c.誤:副作用は容易に異変を自覚できるものばかりではなく、血液や内臓機能への影響のように明確な自覚症状として現れないこともあります。そのため、継続使用の際には異常が感じられなくても医療機関を受診するよう促すことが重要です。
正答:1
問8 医薬品の不適切な使用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 人体に直接使用されない医薬品についても、使用する人の誤解や認識不足によって使い方や判断を誤り、副作用につながることがある。
b 便秘や不眠、頭痛など不快な症状が続くために、長期にわたり連用していても、指示どおりの量の医薬品を使用する場合は、精神的な依存はおこらない。
c 医薬品をみだりに他の医薬品や酒類等と一緒に摂取するといった乱用の繰り返しによって慢性的な臓器障害等を生じることはない。
d 薬物依存とは、ある薬物の精神的な作用を体験するために、その薬物を連続的、あるいは周期的に摂取することへの強迫(欲求)を常に伴っている行動等によって特徴づけられる精神的・身体的な状態をいう。
1( a,b ) 2( a,c ) 3( a,d ) 4( b,c ) 5( c,d )
問8
a.正
b.誤:ブロモバレリル尿素やアリルイソプロピルアセチル尿素などの鎮静成分、コデインリン酸塩水和物やジヒドロコデインリン酸塩などの鎮咳成分 は、いずれも依存性がある成分です。これらの成分は、指示どおりの量であっても反復摂取によって薬物依存の状態になることがあります。
c.誤:医薬品とアルコールの相互作用は、重篤な副作用等に関する情報として挙げられており、腎機能や肝機能の低下など、臓器機能への影響が生じる可能性があります。不適切な使用の繰り返しは、慢性的な臓器障害を含む健康被害につながる危険性があります。
d.正
正答:3
問9 他の医薬品や食品との相互作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 複数の医薬品を併用した場合、又は保健機能食品や、いわゆる健康食品を含む特定の食品と一緒に摂取した場合に、医薬品の作用が増強又は減弱することを相互作用という。
b 相互作用は、医薬品が吸収、分布、代謝(体内で化学的に変化すること)又は排泄される過程で起こるものと、医薬品が薬理作用をもたらす部位において起こるものがある。
c 相互作用を回避するには、ある医薬品を使用している期間やその前後を通じて、その医薬品との相互作用を生じるおそれのある医薬品や食品の摂取を控えなければならないのが通常である。
a b c
1 正 正 誤
2 正 誤 正
3 正 正 正
4 誤 正 誤
5 誤 誤 正
問9
a.正
b.正
c.正
正答:3
問10 他の医薬品や食品との相互作用に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
1 解熱鎮痛薬と鎮静薬では、成分や作用が重複することが多く、通常、これらの薬効群に属する医薬品の併用は避けることとされている。
2 酒類(アルコール)は、医薬品の吸収に影響を与えることはない。
3 医療機関で治療を受けている場合には、通常、その治療が優先されることが望ましく、一般用医薬品を併用しても問題ないかどうかについては、治療を行っている医師若しくは歯科医師、又は処方された医薬品を調剤する薬剤師に確認する必要がある。
4 内服薬だけでなく、外用薬を使用する際も、その作用や代謝について、食品による影響を受ける可能性を考慮する必要がある。
問10
1.正
2.誤:アルコールは胃や小腸で吸収され肝臓で代謝される物質であり、医薬品との相互作用が問題となることが知られています。アルコールは医薬品の吸収、分布、代謝、排泄の過程に影響を与える可能性があります。
3.正
4.正
正答:2
問11 小児の医薬品の使用に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
小児は大人と比べて身体の大きさに対して腸が長く、服用した医薬品の( a )率が相対的に高い。また、血液脳関門が未発達であるため、吸収されて循環血液中に移行した医薬品の成分が脳に達しやすく、( b )神経系に影響を与える医薬品で副作用を起こしやすい。加えて、肝臓や腎臓の機能が未発達であるため、医薬品の成分の( c )に時間がかかり、作用が強く出過ぎたり、副作用がより強く出ることがある。
a b c
1 吸収 中枢 代謝・排泄
2 排泄 末梢 代謝・排泄
3 排泄 中枢 吸収・分布
4 吸収 末梢 吸収・分布
5 吸収 中枢 吸収・分布
問11
a.吸収
b.中枢
c.代謝・排泄
正答:1
問12 高齢者の医薬品の使用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」(平成29年6月8日付け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添)において、おおよその目安として70歳以上を「高齢者」としている。
b よくみられる傾向として、医薬品の説明を理解するのに時間がかかる場合や、細かい文字が見えづらく、添付文書や製品表示の記載を読み取るのが難しい場合等があり、情報提供や相談対応において特段の配慮が必要となる。
c 持病(基礎疾患)を抱えていることが多いため、複数の一般用医薬品を長期にわたって服用することで副作用を防止できる。
d 喉の筋肉が衰えて飲食物を飲み込む力が弱まっている(嚥下障害)場合があり、内服薬を使用する際に喉に詰まらせやすい。
a b c d
1 誤 誤 正 誤
2 正 正 誤 誤
3 正 誤 誤 正
4 誤 正 誤 正
5 誤 正 正 誤
問12
a.誤:「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」において、おおよその目安として65歳以上を「高齢者」としています。
b.正
c.誤:複数の一般用医薬品を長期にわたって服用すると、同じ成分や同種の作用を持つ成分が重複して、効き目が強くなりすぎたり、副作用が起こりやすくなるおそれがあります。
d.正
正答:4
問13 妊婦又は妊娠していると思われる女性及び母乳を与える女性(授乳婦)への医薬品の使用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 胎盤には、胎児の血液と母体の血液とが混ざらない仕組み(血液-胎盤関門)があるが、母体が使用した医薬品の成分が胎児に移行する場合もある。
b 医療用医薬品に限らず、一般用医薬品においても、多くの場合、妊婦が使用した場合における安全性に関する評価が困難であるため、妊婦の使用については「相談すること」としているものが多い。
c 便秘薬を服用する場合は、配合成分やその用量によって流産や早産を誘発するおそれがあるため注意する必要がある。
d 医薬品の種類によっては、授乳婦が使用した医薬品の成分の一部が乳汁中に移行し、母乳を介して乳児が医薬品の成分を摂取することになる場合がある。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 誤 正
3 正 正 誤 誤
4 誤 誤 正 誤
5 正 誤 誤 正
問13
a.正
b.正
c.正
d.正
正答:1
問14 プラセボ効果(偽薬効果)に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果という。
b プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として現れることもあり、その効果を目的として医薬品を使用するべきである。
c プラセボ効果は、条件付けによる生体反応のみが関与して生じると考えられている。
d プラセボ効果によってもたらされる反応や変化には、不都合なもの(副作用)もある。
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 誤 誤
3 正 誤 誤 正
4 正 正 正 正
5 誤 正 誤 正
問14
a.正
b.誤:プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく客観的に測定可能な変化として現れることもありますが、その効果は不確実であり、これを目的として医薬品を使用するべきではありません。
c.誤:プラセボ効果は、医薬品を使用したこと自体による楽観的な結果への期待(暗示効果)や、条件付けによる生体反応、時間経過による自然発生的な変化(自然緩解など)が関与して生じると考えられています。
d.正
正答:3
問15 医薬品の品質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品に配合されている成分は、品質が劣化(変質・変敗)することで、人体に好ましくない作用をもたらす物質を生じることがある。
b 品質が承認された基準に適合しない医薬品は、販売の目的で陳列してはならない。
c 医薬品は、高温、多湿、直射日光等の下に置かないなど適切に保管・陳列していれば、経時変化による品質の劣化は生じない。
d 「使用期限」は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限であり、液剤などでは、いったん開封されると記載されている期日まで品質が保証されない場合がある。
a b c d
1 正 誤 正 正
2 正 誤 誤 誤
3 正 正 誤 正
4 誤 正 正 正
5 誤 正 正 誤
問15
a.正
b.正
c.誤:医薬品は、高温、多湿、直射日光等を避けて適切に保管・陳列したとしても、経時変化による品質の劣化は避けられない。
d.正
正答:3
問16 一般用医薬品に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
一般用医薬品は、医薬品医療機器等法第4条第5項第4号において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )であって、( b )その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(( c )を除く。)」と定義されている。
a b c
1 著しくないもの 薬剤師 薬局医薬品
2 著しくないもの 薬剤師 要指導医薬品
3 著しくないもの 登録販売者 薬局医薬品
4 緩和なもの 薬剤師 薬局医薬品
5 緩和なもの 登録販売者 要指導医薬品
問16
a.著しくないもの
b.薬剤師
c.要指導医薬品
正答:2
問17 一般用医薬品の販売時におけるコミュニケーションにおいて、医薬品の販売等に従事する専門家として留意すべき事項に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 購入者等が、自分自身や家族の健康に対する責任感を持ち、適切な医薬品を選択して、適正に使用するよう、働きかけていくことが重要である。
b 購入者等が医薬品を使用する状況は随時変化する可能性があるため、販売数量は一時期に使用する必要量とする等、販売時のコミュニケーションの機会が継続的に確保されるよう配慮することも重要である。
c 購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しい場合は、購入者側から医薬品の使用状況に係る情報を引き出すべきではない。
d 家庭における常備薬として購入される場合は、すぐ使用されないため、情報提供を行う必要はない。
1( a,b ) 2( a,c ) 3( a,d ) 4( b,c ) 5( b,d )
問17
a.正
b.正
c.誤:医薬品の販売に従事する専門家は、購入者のニーズや購入動機、使用者の情報、過去のアレルギーや副作用経験、他の医薬品や食品の摂取状況など、基本的なポイントを確認することが求められています。
d.誤:一般用医薬品が家庭における常備薬として購入されることも多いため、外箱等に記載されている使用期限から十分な余裕をもって販売等がなされることが重要とされています。これは情報提供が不要であることを意味せず、むしろ適切な情報提供を通じて長期的な品質保持や適正使用を促す必要があります。
正答:1
問18 一般用医薬品の販売時におけるコミュニケーションにおいて、医薬品の販売等に従事する専門家として留意すべき事項に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 登録販売者は、生活者のセルフメディケーションに対して、すべての一般用医薬品の販売や情報提供を担う観点から、支援していくという姿勢で臨むことが基本となる。
b 医薬品の販売等に従事する専門家が購入者等から確認しておきたい基本的なポイントの1つとして、購入者等のニーズや購入の動機など、何のためにその医薬品を購入しようとしているかという点がある。
c 医薬品の販売に従事する専門家は、必ずしも情報提供を受けた当人が医薬品を使用するとは限らないことを踏まえ、販売時のコミュニケーションを考える必要がある。
d 医薬品の販売に従事する専門家が、購入者側の状況を把握するため購入者等に尋ねる場合は、一般用医薬品の使用状況のみを簡潔に確認するよう努める必要がある。
a b c d
1 正 誤 正 正
2 誤 誤 正 正
3 正 正 誤 誤
4 誤 正 正 誤
5 正 正 誤 正
問18
a.誤:登録販売者が販売や情報提供を担うことができるのは、第二類医薬品および第三類医薬品です。第一類医薬品の販売や情報提供は薬剤師が担います。したがって、すべての一般用医薬品を担うという記述は誤りです。
b.正
c.正
d.誤:医薬品の販売等に従事する専門家が確認すべき基本的なポイントには、購入者のニーズ、使用者の情報(小児や高齢者、妊婦など)、医療機関での治療の有無、過去のアレルギーや副作用経験、他の医薬品や食品の摂取状況など、複数の事項が含まれます。一般用医薬品の使用状況のみを簡潔に確認するという記述は不十分です。
正答:4
問19 HIV(ヒト免疫不全ウイルス)訴訟に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
1 HIV訴訟は、血友病患者が、HIVが混入した原料血漿から製造された免疫グロブリン製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。
2 HIV訴訟は、国及び製薬企業を被告として、1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁で提訴され、両地裁は、1995年10月、1996年3月にそれぞれ和解勧告を行い、1996年3月に両地裁で和解が成立した。
3 国は、HIV感染者に対する恒久対策として、エイズ治療・研究開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取り組みを推進している。
4 HIV訴訟を契機に、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られた。
問19
1.誤:HIV訴訟は、血友病患者がヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿から製造された血液凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟であるとされています。
2.正
3.正
4.正
正答:1
問20 医薬品による副作用等にかかる訴訟に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a スモン訴訟は、整腸剤として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。
b キノホルム製剤は、1924年から整腸剤として販売されていたが、日本では1960年にアメーバ赤痢への使用に限ることが勧告され、米国では、1970年8月になって、スモンの原因はキノホルムであるとの説が発表され、同年9月に販売が停止された。
c スモン訴訟により、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度が創設された。
d サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、1979年に医薬品副作用被害救済制度が創設された。
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 誤 正
3 誤 誤 正 正
4 誤 正 正 誤
5 正 誤 誤 正
問20
a.正
b.誤: キノホルム製剤は、1924年から整腸剤として販売されていたが、米国では1960年にアメーバ赤痢への使用に限ることが勧告され、日本では、1970年8月になって、スモンの原因はキノホルムであるとの説が発表され、同年9月に販売が停止された。
c.誤:緊急輸入制度の創設は、HIV訴訟を契機とした医薬品の副作用等による健康被害の再発防止に向けた取り組みの一環として行われました。
d.正
正答:5
他の問題・解説はこちらへ→ 一 覧

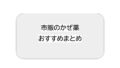

コメント