他の問題・解説はこちらへ→ 一 覧
問101 医薬品の適正使用情報に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 重篤な副作用として、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症等が掲げられている医薬品では、添付文書等における「使用上の注意」の欄に、アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されている。
b 登録販売者は、添付文書や製品表示の内容を的確に理解した上で、その医薬品を使用する個々の生活者の状況に応じて、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明を行うことが重要である。
c 医薬品医療機器等法第52条第2項の規定により、一般用医薬品には、それに添付する文書又はその容器若しくは被包に、「用法、用量及び製造年月日」の記載が義務づけられている。
d 要指導医薬品の添付文書に記載されている適正使用情報は、専門的な表現で記載されているため、一般の生活者には理解しにくいものになっている。
1(a、b)
2(a、c)
3(a、d)
4(b、c)
5(c、d)
問101
a.正
b.正
c.誤:添付文書等には「用法用量その他使用及び取扱い上必要な注意等」が記載されなければならないとされていますが、「製造年月日」の記載義務はありません。法定表示事項としては「製造番号又は製造記号」と「使用の期限」が挙げられています。
d.誤:適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要であるため、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとなっている。
正答:1
問102 一般用医薬品(人体に直接使用しない検査薬を除く。)の添付文書に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見を反映するため、3年ごとに定期的な改訂がなされている。
b 添付文書は開封時に一度目を通されれば十分というものではなく、必要なときにいつでも取り出して読むことができるように保管される必要がある。
c 一般用医薬品を使用した人が医療機関を受診する際は、その添付文書を持参し、医師や薬剤師に見せて相談がなされることが重要である。
d 販売名に薬効名が含まれているような場合には、薬効名の記載は省略されることがある。
a b c d
1 正 誤 誤 正
2 誤 正 正 正
3 正 正 誤 誤
4 誤 誤 正 誤
5 正 正 正 誤
問102
a.誤:添付文書の内容は「最新の論文その他により得られた知見に基づき」記載されなければならないとされており、新たな知見が反映されることで随時改訂されます。
b.正
c.正
d.正
正答:2
問103 一般用医薬品(人体に直接使用しない検査薬を除く。)の添付文書等に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 使用上の注意は、「相談すること」、「してはいけないこと」、「その他の注意」の順に記載するよう定められている。
b 一般用医薬品のうち第三類医薬品については、製品のリスク区分の記載を省略することができる。
c 点眼剤に類似した容器に収められた外用液剤では、取り違えにより点眼される事故防止のため、その容器本体に赤枠・赤字で「目に入れない」旨の文字が記載されている。
d 成分及び分量には、有効成分の名称及び分量の記載と併せて、添加物として配合されている成分が掲げられている。
1(a、b)
2(a、c)
3(a、d)
4(b、d)
5(c、d)
問103
a.誤: 使用上の注意は、「してはいけないこと」、「相談すること」、「その他の注意」の順に記載するよう定められている。適正使用のために重要と考えられる項目が前段に記載されている。
b.誤:一般用医薬品のリスク区分を示す字句は法定表示事項の一つであり、第三類医薬品を含むすべての一般用医薬品について記載が義務付けられています。省略はできません。
c.正
d.正
正答:5
問104 一般用医薬品の保管及び取扱い上の注意に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 点眼薬では、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に別の使用者に感染するおそれがあるため、添付文書に「家族以外の人とは共用しないこと」と記載されている。
b ビン入りの錠剤は、旅行や勤め先等へ携行する場合、市販の容器に移し替えることが適当である。
c 可燃性ガスを噴射剤としているエアゾール製品については、消防法(昭和23年法律第186号)や高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づき、その容器への注意事項の表示が義務づけられているが、添付文書において「保管及び取扱い上の注意」としても記載されている。
d 小児に使用される医薬品を除き、医薬品は小児の手の届かないところに保管される必要がある。
a b c d
1 誤 正 誤 正
2 正 正 正 誤
3 正 誤 誤 誤
4 誤 誤 正 誤
5 正 誤 正 正
問104
a.誤:点眼薬では、複数の使用者間で使い回されると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に、別の使用者に感染するおそれがあるため、「他の人と共用しないこと」と記載されている。
b.誤:「他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)」と明確に記載されており、旅行等で別の容器に移し替えることは、誤用の原因となったり、品質が保持できなくなるおそれがあるため不適当とされています。
c.正
d.誤:小児用医薬品であっても、子供が誤って過量に摂取するリスクがあるため、適切に管理される必要があります。
正答:4
問105 次の医薬品成分のうち、一般用医薬品の添付文書等において、眠気、目のかすみ、異常なまぶしさを生じることがあるため、「してはいけないこと」の項目中に「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」と記載することとされている成分はどれか。
1 テオフィリン
2 スコポラミン臭化水素酸塩水和物
3 ケトプロフェン
4 カフェイン
5 プソイドエフェドリン塩酸塩
問105
1.誤:気管支拡張作用を持つ成分
2.正:スコポラミン臭化水素酸塩水和物は抗コリン作用を持つ成分であり、この作用によって上記の副作用が生じます。
3.誤:非ステロイド性抗炎症成分
4.誤:眠気を防ぐ目的で配合される成
5.誤:アドレナリン作動成分で鼻粘膜の充血を和らげる作用
正答:2
問106 次の医薬品成分のうち、一般用医薬品の添付文書等において、妊娠期間の延長、胎児の動脈管の収縮・早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加のおそれがあるため、「次の人は服用しないこと」の項目中に「出産予定日12週以内の妊婦」と記載することとされている成分はどれか。
1 アミノ安息香酸エチル
2 エチニルエストラジオール
3 アスピリンアルミニウム
4 ビタミンA
5 ジヒドロコデインリン酸塩
問106
1.誤:アミノ安息香酸エチルは、「6歳未満の小児」に対してメトヘモグロビン血症を起こすおそれがあるため使用を避けるべきとされています。
2.誤:エチニルエストラジオールは、「妊婦又は妊娠していると思われる人」に対して妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって胎児の先天性異常の発生が報告されているため使用を避けるべきとされています。
3.正:アスピリン、アスピリンアルミニウム、イブプロフェンは、妊娠期間の延長、胎児の動脈管の収縮・早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加のおそれがあるためです。
4.誤:ビタミンA(ビタミンA主薬製剤、ビタミンAD主薬製剤)は、「妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人」に対して先天異常の発生率増加が報告されているため使用を避けるべきとされています。
5.誤:ジヒドロコデインリン酸塩は、「妊婦又は妊娠していると思われる人」に対して麻薬性鎮咳成分であり、胎盤関門を通過して胎児へ移行するおそれがあるため使用を避けるべきとされています。
正答:3
問107 次の医薬品の販売等に従事する登録販売者と購入者の会話のうち、購入者からの相談に対する登録販売者の対応の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 購 入 者:「授乳中なのですが、便秘がひどいので、薬を購入したいです。」
登録販売者:「センノシドが配合された便秘薬は、授乳中でも服用できます。」
b 購 入 者:「ジフェンヒドラミン塩酸塩を主薬とする催眠鎮静薬の購入を考えていますが、お酒が好きで、毎日晩酌しています。注意することはありますか。」
登録販売者:「鎮静作用の増強が生じるおそれがあるので、服用前後は飲酒しないでください。」
c 購 入 者:「部活のため、屋外において毎日サッカーをしています。ふくらはぎの筋肉痛に、ケトプロフェンが配合された外用鎮痛消炎薬の使用を検討しています。」
登録販売者:「屋外において使用する場合は、使用中又は使用後しばらくしてから重篤な光線過敏症が現れることがあるため、ケトプロフェンが配合されていない外用鎮痛消炎薬を使用してください。」
d 購 入 者:「大型トラックの運転手として働いています。運転中に眠くなるのを避けるため、初めてカフェイン入り眠気防止薬を飲んでみようと思っています。」
登録販売者:「カフェイン入り眠気防止薬は、一時的に居眠りを防止することが目的です。服用する際は、短期間の服用にとどめ、長期連用はせず、また、コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。」
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 正 正 誤 正
3 誤 誤 誤 正
4 誤 正 誤 誤
5 誤 正 正 正
問107
a.誤:瀉下作用のある医薬品成分(ダイオウ、センノシドなど)については、授乳中の女性における使用に際して留意が必要とされています。
b.正
c.正
d.正
正答:5
問108 一般用医薬品の添付文書等の「相談すること」の項目中に「次の診断を受けた人」と記載することとされている医薬品成分等と基礎疾患等の組合せの正誤について、正しい組合せはどれか。
医薬品成分等 基礎疾患等
a マオウ ―――――――――――――― 貧血
b アセトアミノフェン ―――――――― 胃・十二指腸潰瘍
c メチルエフェドリン塩酸塩 ――――― 糖尿病
d エテンザミド ――――――――――― 腎臓病
a b c d
1 正 正 誤 誤
2 誤 正 正 正
3 誤 誤 正 誤
4 誤 正 誤 誤
5 正 誤 誤 正
問108
a.誤:マオウは、心臓病の診断を受けた人が相談することとされている。
b.正
c.正
d.正
正答:2
問109 次の表は、ある一般用医薬品の制酸薬に含まれている成分の一覧である。この制酸薬の添付文書等の「相談すること」の項目中に「次の診断を受けた人」として記載されている基礎疾患等はどれか。
1日量(6錠)中
水酸化マグネシウム 450mg
合成ヒドロタルサイト 780mg
沈降炭酸カルシウム 900mg
アルジオキサ 150mg
ピレンゼピン塩酸塩水和物 46.9mg
炭酸水素ナトリウム 240mg
チンピ末 300mg
1 糖尿病
2 腎臓病
3 高血圧
4 てんかん
5 肝臓病
問109
1.誤
2.正
3.誤
4.誤
5.誤
成分リストには、水酸化マグネシウム、合成ヒドロタルサイト、沈降炭酸カルシウム、アルジオキサが含まれています。
• マグネシウムを含む成分(水酸化マグネシウムなど)については、「腎臓病の診断を受けた人では、高マグネシウム血症を生じるおそれがある」ため、使用前に相談がなされるべきとされています。
• アルミニウムを含む成分(合成ヒドロタルサイト、アルジオキサなど)については、「腎臓病の診断を受けた人」や「透析療法を受けている人」が長期間服用した場合に、アルミニウム脳症及びアルミニウム骨症を引き起こすおそれがあるため、使用前に相談がなされるべきとされています。
• カルシウムを含む成分(沈降炭酸カルシウムなど)も腎臓病患者に注意が必要な場合がありますが、主な注意喚起はマグネシウム・アルミニウム関連成分と共通しています。
正答:2
問110 一般用医薬品の添付文書等の「相談すること」の項目中に「次の診断を受けた人」として「甲状腺機能障害又は甲状腺機能亢進症」と記載することとされている医薬品成分とその理由の組合せの正誤について、正しい組合せはどれか。
医薬品成分 理由
a トリメトキノール塩酸塩水和物 ― 交感神経系の興奮作用により、症状を悪化させるおそれがあるため。
b 沈降炭酸カルシウム ―――――― 甲状腺ホルモンの吸収を阻害するおそれがあるため。
c フェニレフリン塩酸塩 ――――― 副交感神経系の興奮作用により、症状を悪化させるおそれがあるため。
a b c
1 誤 誤 正
2 正 正 誤
3 正 誤 誤
4 正 正 正
5 誤 正 誤
問110
a.正:トリメトキノール塩酸塩水和物はアドレナリン作動成分であり、交感神経系を興奮させる作用があります。
b.正
c.誤:フェニレフリン塩酸塩はアドレナリン作動成分であり、交感神経系を興奮させる作用を示します。
正答:2
問111 医薬品等の安全性情報等に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 緊急安全性情報は、ブルーレターとも呼ばれる。
b 緊急安全性情報は、医療機関や薬局等へ直接配布されるものであり、電子メールによる情報伝達は認められていない。
c 安全性速報の対象となるのは、医薬品だけでなく、医療機器や再生医療等製品も対象となる。
d 緊急安全性情報及び安全性速報は、厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。
1(a、b)
2(a、c)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問111
a.誤: 緊急安全性情報は、イエローレターとも呼ばれる。安全性速報がブルーレターと呼ばれている。
b.誤:医療機関や薬局等への直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電子メール等による情報提供(1ヶ月以内)等により情報伝達されるものである。
c.正
d.正
正答:5
問112 医薬品の添付文書情報等の活用に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 令和3年8月1日から、医療用医薬品への紙の添付文書の同梱を廃止し、注意事項等情報は電子的な方法により提供されることとなったが、一般用医薬品等の製品は、引き続き紙の添付文書が同梱されている。
b 独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページでは、一般用医薬品・医療用医薬品の添付文書情報を閲覧することができる。
c 添付文書に「使用上の注意」として記載される内容は、その医薬品に配合されている成分等に由来することが多い。
a b c
1 正 正 正
2 正 誤 誤
3 正 正 誤
4 誤 誤 正
5 誤 正 誤
問112
a.正
b.正
c.正
正答:1
問113 医薬品の副作用情報等の収集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業は、当該製品の安全性について評価し、その成果が副作用情報として有用であったときに速やかに報告すれば、定期的に国へ報告する必要はない。
b 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度において、実務上は、医薬品医療機器等法第68条の13第3項の規定により、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとされている。
c 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、1967年より、厚生省(当時)が全ての医療機関から直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
d 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告を行う医薬関係者には、登録販売者が含まれる。
1(a、b)
2(a、c)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問113
a.誤:生物由来製品、特に特定生物由来製品は、感染症のリスクに着目して厳重な規制が課されており、製造販売後に感染症に関する定期的な報告を国(厚生労働大臣)に行うことが義務付けられています。
b.正
c.誤:1967年3月より、約3000の医療機関をモニター施設に指定して、厚生省(当時)が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
d.正
正答:4
問114 企業からの副作用等の報告制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 登録販売者は、製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならない。
b 製造販売業者は、製造販売をした医薬品について、その副作用によるものと疑われる健康被害の発生を知った時に医薬品医療機器等法に基づき報告することが義務づけられているが、報告期限は定められていない。
c 一般用医薬品では、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね8年)、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度(再審査制度)が適用される。
d 医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として承認後の一定期間(概ね3年)、品質及び有効性に関する調査及び調査結果の報告が求められている。
a b c d
1 誤 正 正 誤
2 正 正 誤 正
3 正 誤 正 正
4 正 誤 正 誤
5 誤 誤 誤 正
問114
a.正
b.誤:「企業からの副作用等の報告」は、副作用症例の重篤性や予測の有無に応じて、「15日以内」または「30日以内」の報告期限が明確に定められています。
c.正
d.誤:、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として承認後の一定期間(概ね3年)、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められている。
正答:4
問115 医薬品の副作用情報等の評価及び措置に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において行われた調査検討の結果に基づき、日本製薬団体連合会の意見を聴いて、安全対策上必要な行政措置を講じている。
b 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、薬事審議会の意見を聴いて、調査・実験の実施の指示、製造・販売の中止、製品の回収等の安全対策上必要な措置を講じている。
c 収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が図られる。
d 厚生労働省の健康危機管理に当たっては、科学的・客観的な評価を行うとともに、情報の広範な収集、分析の徹底と対応方針の弾力的な見直しに努め、国民に対して情報の速やかな提供と公表を行うことを基本としている。
1(a、c)
2(a、d)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問115
a.誤:安全対策上必要な行政措置を講じるのは厚生労働大臣ですが、その際に意見を聴くのは薬事審議会であり、日本製薬団体連合会ではありません。
b.誤:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、副作用や感染症の発生状況等の調査検討を行う役割を担っていますが、安全対策上必要な行政措置(例えば、承認条件の変更や販売中止等)を講じるのは厚生労働大臣です。
c.正
d.正
正答:5
問116 医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等の報告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品によるものと疑われる死亡事例のほか、日常生活に支障を来す程度の健康被害についても報告が求められている。
b 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の誤用によるものと思われる健康被害についても報告がなされる必要がある。
c 医薬品の副作用は、使用上の注意に記載されているものに限る。
d 医薬品と副作用の因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る。
a b c d
1 正 正 誤 正
2 正 正 正 正
3 誤 誤 誤 正
4 正 誤 正 誤
5 誤 正 正 誤
問116
a.正
b.正:安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても報告が求められています。
c.誤:医薬品と副作用の因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る、とされており、使用上の注意に記載されているものに限定されません。
d.正
正答:1
問117 医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合について、被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として運用が開始された。
b 医薬品を適正に使用した場合であっても、要指導医薬品又は一般用医薬品の一部には、救済制度の対象とならない医薬品がある。
c 健康被害を受けた本人(又は家族)への給付は、医学的薬学的判断を要する事項について薬事審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて行われる。
d 給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があり、給付の種類によっては請求期限が定められているため、注意する必要がある。
a b c d
1 誤 正 誤 誤
2 誤 誤 正 正
3 正 誤 誤 正
4 正 誤 正 誤
5 正 正 正 正
問117
a.正
b.正:救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。
c.正
d.正
正答:5
問118 医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合についても、救済給付の対象となる。
b 個人輸入により入手した医薬品を使用して生じた健康被害は、救済制度の対象となる。
c 医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は、給付請求を行うことはできない。
d 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されている。
1(a、c)
2(a、d)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問118
a.正
b.誤:個人輸入された医薬品の使用による健康被害については救済制度の対象から除外されています。
c.誤:医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合でも、給付請求を行うことは可能であるとされています。
d.正:医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨されます。
正答:2
問119 一般用医薬品の安全対策に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 一般用かぜ薬の使用によると疑われる肝機能障害の発生事例が報告されたことを受けて、2003年に厚生労働省は、一般用かぜ薬全般につき使用上の注意の改訂を指示することとした。
b 慢性肝炎患者が小青竜湯を使用して間質性肺炎を発症し、死亡を含む重篤な転帰に至った例もあったことから、厚生省(当時)より関係製薬企業に対して緊急安全性情報の配布が指示された。
c 解熱鎮痛成分としてアミノピリン等が配合されたアンプル入りかぜ薬の使用による重篤な副作用(ショック)が発生したことから、厚生省(当時)より関係製薬企業に対し、製品の回収が要請された。
d 塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)が配合された一般用医薬品による脳出血等の副作用症例が複数報告されたことから、厚生労働省は、代替成分としてプソイドエフェドリン塩酸塩等への速やかな切替えを指示した。
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 正 誤
3 正 誤 誤 誤
4 誤 誤 正 正
5 正 正 誤 正
問119
a.誤: 一般用かぜ薬の使用によると疑われる間質性肺炎の発生事例が報告されたことを受けて、2003年に厚生労働省は、一般用かぜ薬全般につき使用上の注意の改訂を指示することとした。
b.誤:慢性肝炎患者が小柴胡湯を使用して間質性肺炎を発症し、死亡を含む重篤な転帰に至った例もあったことから、厚生省(当時)より関係製薬企業に対して緊急安全性情報の配布が指示された。
c.正
d.正
正答:4
問120 医薬品の適正使用のための啓発活動等に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 登録販売者は、適切なセルフメディケーションの普及定着、医薬品の適正使用の推進のため、啓発活動に積極的に参加、協力することが期待される。
b 薬物乱用や薬物依存は、違法薬物(麻薬、覚醒剤、大麻等)によるもので、一般用医薬品によっては生じ得ない。
c 医薬品の適正使用の重要性に関する啓発は、内容が正しく理解されないおそれがあるため、小中学生に行うべきではない。
d 毎年10月17日~23日の1週間を「薬と健康の週間」として、国、自治体、関係団体等による広報活動やイベント等が実施されている。
a b c d
1 正 誤 誤 誤
2 誤 正 誤 正
3 正 誤 誤 正
4 誤 誤 正 誤
5 正 正 正 誤
問120
a.正
b.誤:薬物乱用や薬物依存は、違法薬物によるものだけでなく、一般用医薬品によっても生じ得るとされています。
c.誤:医薬品の適正使用の重要性に関して、小中学生のうちからの啓発が重要であるとされています。
d.正
正答:3
他の問題・解説はこちらへ→ 一 覧


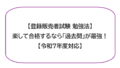
コメント