他の問題・解説はこちらへ→ 一 覧
問41 医薬品の適正使用情報に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要な情報(適正使用情報)を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。
b 要指導医薬品又は一般用医薬品の場合、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、薬剤師、登録販売者その他の医薬関係者が一般の生活者へ提供する情報のため、専門的・部分的なものである。
c 医薬品の販売等に従事する専門家においては、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
d 要指導医薬品は、医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものである。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 正 正
3 正 誤 正 正
4 正 正 誤 正
5 正 正 正 誤
問41
a.正
b.誤:情報自体が「専門的・部分的なもの」とは書かれておらず、むしろ一般の生活者には分かりにくいことがあるという点が強調されています。
c.正
d.正
正答:3
問42 一般用医薬品の添付文書に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、1年に1回定期的に改訂されている。
b 重要な内容が変更された場合には、改訂年月を記載するとともに改訂された箇所を明示することとされている。
c 一般用医薬品のリスク区分の記載は省略されることがある。
d 販売名に薬効名が含まれているような場合には(例えば、「〇〇胃腸薬」など)、薬効名の記載は省略されることがある。
1(a、b)
2(a、c)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問42
a.誤
b.正
c.誤:一般用医薬品のリスク区分を示す字句は、法定表示事項として記載が義務付けられています。
d.正
正答:4
問43 次のうち、一般用医薬品の添付文書を構成する項目として、正しいものの組み合わせはどれか。
a 製造年月日
b 製品の特徴
c 消費者相談窓口
d 製造所の許可番号
1(a、b)
2(a、c)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問43
a.誤
b.正
c.正
d.誤
正答:3
問44 一般用医薬品の添付文書における使用上の注意の記載に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」から構成され、適正使用のために重要と考えられる項目が前段に記載されている。
b 一般用検査薬では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が陽性であれば速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。
c 「次の人は使用(服用)しないこと」の項目は、その医薬品の使用によって状態が悪化するおそれのある疾病や症状で、一般の生活者において誤って使用されやすいものがある場合にも、適正使用を図る観点から記載されている。
d 小児に使用される医薬品においては、小児では通常当てはまらない「服用前後は飲酒しないこと」の記載はされない。
a b c d
1 正 正 正 誤
2 誤 正 誤 誤
3 正 正 誤 正
4 誤 誤 正 正
5 正 誤 誤 誤
問44
a.正
b.正
c.正
d.誤
正答:1
問45 次の一般用医薬品の医薬品成分のうち、アスピリン喘息を誘発するおそれがあるため、その添付文書の「次の人は使用(服用)しないこと」の項目に、「本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を使用(服用)して喘息を起こしたことがある人」と記載することとされているものとして、正しいものの組み合わせはどれか。
a アセトアミノフェン
b イソプロピルアンチピリン
c アミノ安息香酸エチル
d カフェイン
1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
問45
a.正
b.正
c.誤
d.誤
正答:1
問46 次の1~5で示される医薬品成分のうち、外国において、ライ症候群の発症との関連性が示唆されているため、一般用医 薬品の添付文書の「次の人は使用(服用)しないこと」の項目に、「15歳未満の小児」と記載することとされているものはどれか。
1 アスピリンアルミニウム
2 チペピジンヒベンズ酸塩
3 センノシド
4 ジフェニドール塩酸塩
5 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
問46
「水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)」に対しては、サリチルアミドやエテンザミドの使用を避ける必要があるとされています。これは、構造が類似しているアスピリンにおいて、ライ症候群の発症との関連性が示唆されているためです。アスピリンアルミニウムはアスピリンの誘導体であり、この注意喚起の対象となります。
正答:1
問47 次の一般用医薬品の医薬品成分のうち、長期間服用した場合に、アルミニウム脳症及びアルミニウム骨症を発症したとの報告があるため、その添付文書の「してはいけないこと」の項において、「次の人は使用(服用)しないこと」の項目欄に、「透析療法を受けている人」と記載することとされているものとして、正しいものの組み合わせはどれか。
a セトラキサート塩酸塩
b ピロキシカム
c アルジオキサ
d スクラルファート
1(a、b)
2(a、c)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問47
アルミニウムを含む成分について、透析療法を受けている人が長期間服用した場合にアルミニウム脳症およびアルミニウム骨症を引き起こしたとの報告があり、透析療法を受けている人では使用を避ける必要があるとされています。
a.誤
b.誤
c.正
d.正
正答:5
問48 一般用医薬品の添付文書の「相談すること」の項目中に、「次の診断を受けた人」と記載される基礎疾患等と、主な成分・薬効群等との関係について、正しいものの組み合わせはどれか。
基礎疾患等 主な成分・薬効群等
a てんかん ― ジプロフィリン
b 高血圧 ― ロペラミド塩酸塩
c 糖尿病 ― セトラキサート塩酸塩
d 甲状腺機能障害 ― 乳酸カルシウム水和物
1(a、b)
2(a、c)
3(a、d)
4(b、d)
5(c、d)
問48
a.正:ジプロフィリンは甲状腺機能障害も対象。
b.誤:高血圧はマオウなど
c.誤:糖尿病はメチルエフェドリンなど。セトラキサートは血栓がある人などが対象。
d.正
正答:3
問49 次の表は、ある解熱鎮痛薬に含まれている成分(一部抜粋)である。
2錠中
イブプロフェン 150mg
アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg
無水カフェイン 80mg
次のうち、この解熱鎮痛薬を服用するにあたって注意すべき事項の説明として、正しいものの組み合わせはどれか。
a イブプロフェンが含まれているため、出産予定日12週以内の妊婦は、服用しないこととされている。
b イブプロフェンが含まれているため、肝臓病の診断を受けた人は、服用前に専門家に相談することとされている。
c アリルイソプロピルアセチル尿素が含まれているため、てんかんの診断を受けた人は、服用前に専門家に相談することとされている。
d 無水カフェインが含まれているため、緑内障の診断を受けた人は、服用前に専門家に相談することとされている。
1(a、b)
2(a、c)
3(a、d)
4(b、d)
5(c、d)
問49
a.正
b.正
c.誤:アリルイソプロピルアセチル尿素は鎮静成分であり依存性がある とされています。
d.誤:緑内障の悪化を招く成分としては、パパベリン塩酸塩 や抗コリン成分 が挙げられています。
正答:1
問50 一般用医薬品の添付文書における使用上の注意に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a オキセサゼインは、妊娠中における安全性が確立されていないため、妊婦又は妊娠していると思われる人は、服用しないこととされている。
b 小柴胡湯は、無菌性髄膜炎の副作用を起こしやすいため、混合性結合組織病の診断を受けた人は、相談することとされている。
c セトラキサート塩酸塩は、出血傾向を増悪させるおそれがあるため、血液凝固異常の診断を受けた人は、相談することとされている。
d 芍薬甘草湯は、徐脈又は頻脈を引き起こし、心臓病の症状を悪化させるおそれがあるため、心臓病の診断を受けた人は、服用しないこととされている。
1(a、b)
2(a、d)
3(b、c)
4(c、d)
問50
a.正
b.誤:柴胡湯は間質性肺炎の重篤な副作用が知られている。
c.誤:セトラキサート塩酸塩は、血栓を分解しにくくするおそれがあるため
d.正
正答:2
問51 一般用医薬品の添付文書に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 添付文書の販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。」等の文言が記載されている。
b 使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として75歳以上を指す。
c 漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。
d 薬理作用等から発現が予測される軽微な症状がみられた場合に関する記載として、症状の持続又は増強がみられた場合には、使用を自己判断で中止することなく、専門家に相談する旨が記載されている。
a b c d
1 誤 誤 誤 誤
2 誤 正 誤 正
3 正 誤 正 誤
4 正 正 誤 誤
5 誤 誤 正 正
問51
a.正
b.誤:使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として65歳以上を指します。
c.正
d.誤:一旦、使用を中止する。
正答:3
問52 緊急安全性情報に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a A4サイズの青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれる。
b 医療用医薬品や医家向け医療機器についての情報伝達であり、一般用医薬品に関する緊急安全性情報が発出されたことはない。
c 厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。
d 製造販売業者及び行政当局による報道発表、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品医療機器情報配信サービスによる配信、製造販売業者から医療機関や薬局等への直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電子メール等による情報提供(1ヶ月以内)等により情報伝達されるものである。
1(a、b)
2(a、c)
3(b、c)
4(b、d)
5(c、d)
問52
a.誤:イエローと呼ばれている。
b.誤:一般用医薬品に関しても重篤な副作用事例などがあった場合には、緊急安全性情報が発出されることがあります。
c.正
d.正
正答:5
問53 医薬品・医療機器等安全性情報に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況にある場合のみ作成される。
b 厚生労働省が情報をとりまとめ、広く医薬関係者向けに情報提供を行っている。
c 医薬品の安全性に関する解説記事や、使用上の注意の改訂内容、主な対象品目、参考文献等が掲載されている。
d 各都道府県、保健所設置市及び特別区、関係学会等へ冊子が送付されているほか、厚生労働省ホームページ及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページへ掲載されるとともに、医学・薬学関係の専門誌等にも転載される。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 正 正
3 正 誤 正 正
4 正 正 誤 正
5 正 正 正 誤
問53
a.誤:緊急かつ重大な注意喚起が必要な場合に限定されず、より広範な安全性に関する情報(解説記事や使用上の注意の改訂内容など)が提供されます。
b.正
c.正
d.正
正答:2
問54 医薬品の副作用情報等の収集に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 製造販売業者には、医薬品との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等について、国への報告義務が課せられている。
b 一般用医薬品では、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね8年)、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する再審査制度が適用される。
c 医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として承認後の一定期間(概ね3年)、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められている。
d 登録販売者は、製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならない。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 正 正
3 正 誤 正 正
4 正 正 誤 正
5 正 正 正 誤
問54
a.正
b.正
c.正
d.正
正答:1
問55 医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、登録販売者が行う医薬品の副作用等報告に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 報告様式は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページから入手できる。
b 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る。
c 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、報告される必要がある。
d 令和3年4月から、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能となった。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 正 正
3 正 誤 正 正
4 正 正 誤 正
5 正 正 正 誤
問55
a.正
b.正
c.正
d.正
正答:1
問56 医薬品医療機器等法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、その製造販売した医薬品について行う副作用等の報告において、その発生を知ったときは15日以内に厚生労働大臣に報告することとされている事例に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡に至った国内事例
b 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例
c 医薬品による ものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもので、重篤(死亡を含む)な国内事例
d 外国における製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施事例
a b c d
1 正 誤 正 正
2 誤 正 誤 正
3 正 正 誤 誤
4 誤 誤 正 正
5 正 誤 誤 誤
問56
a.正
b.誤:定期報告でよい。
c.正
d.正
正答:1
問57 医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 副作用による疾病のため入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も救済給付の対象となる。
b 個人輸入した医薬品の使用による健康被害は救済制度の対象とならない。
c いわゆる健康食品の使用による健康被害は救済制度の対象となる。
d 医療機関での治療を要さず寛解したような軽度な健康被害についても救済給付の対象となる。
1(a、b)
2(a、d)
3(b、c)
4(c、d)
問57
a.正
b.正
c.誤:救済制度は「医薬品」の副作用による健康被害を対象としています。健康食品は医薬品とは法律上区別される食品であり、救済制度の対象外です。
d.誤:救済給付の対象となる健康被害の程度は、「入院を必要とする程度」と明確に定められています。軽度な健康被害は対象外です。
正答:1
問58 医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があり、すべて請求期限が定められている。
b 一般用検査薬を適正に使用したにもかかわらず、健康被害を生じた場合は救済制度の対象となる。
c 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)等のほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
d 日本薬局方に収載されている医薬品はすべて救済制度の対象となる。
a b c d
1 正 誤 正 正
2 誤 正 誤 誤
3 正 正 正 正
4 誤 誤 正 誤
5 正 誤 誤 誤
問58
a.誤:障害年金と障害児養育年金は「請求期限なし」と明記されています。
b.誤:救済制度は「副作用による疾病」を対象としています。検査薬による健康被害は、主に診断の誤りによる治療機会の損失などが考えられ、一般的に検査薬の健康被害は「副作用」として扱われないことが多いです。
c.正
d.誤:救済制度の対象となるのは「適正に使用」され、かつ「入院治療を必要とする程度」の健康被害が生じた場合に限られます。したがって、「すべて」対象となるわけではありません。
正答:4
問59 一般用医薬品の安全対策等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a アンプル入りかぜ薬は他の剤形(錠剤、散剤等)に比べて吸収が速く、通常用量でも副作用を生じやすいことが確認されたことから、厚生省(当時)より関係製薬企業に対し、アンプル入りかぜ薬製品の回収が要請された。
b 小柴胡湯とインターフェロン製剤との併用を禁忌とする旨の使用上の注意の改訂後も慢性肝炎患者が小柴胡湯を使用して間質性肺炎を発症し、死亡を含む重篤な転帰に至った例がある。
c プソイドエフェドリン塩酸塩が配合され た一般用医薬品による脳出血等の副作用症例が複数報告されたことを受け、厚生労働省から関係製薬企業等に対して、使用上の注意の改訂、情報提供の徹底等を行うとともに、代替成分として塩酸フェニルプロパノールアミンへの 速やかな切替えについて指示がなされた 。
d 一般用かぜ薬全般において、まれに間質性肺炎の重篤な症状が起きることがあり、その症状は、かぜの諸症状と区別が難しいため、症状が悪化した場合には服用を中止して医師の診療を受ける旨の注意喚起がなされている。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 正 正
3 正 誤 正 正
4 正 正 誤 正
5 正 正 正 誤
問59
a.正
b.正
c.誤:脳出血のリスクが問題視され、代替成分への切替えが指示されたのは、塩酸フェニルプロパノールアミンが原因成分として指摘されたことによるものであり、プソイドエフェドリン塩酸塩がその代替成分として導入された経緯があります。
d.正
正答:4
問60 医薬品の適正使用及びその啓発活動に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品の持つ特質及びその使用・取扱い等について正しい知識を広く生活者に浸透させることにより、保健衛生の維持向上に貢献することを目的とし、毎年10月17日~23日の1週間を「薬と健康の週間」として、広報活動やイベント等が実施されている。
b 薬物乱用や薬物依存は、違法薬物(麻薬、覚醒剤、大麻等)によるものばかりでなく、一般用医薬品によっても生じ得る。
c 医薬品の適正使用の重要性等に関して、小中学生のうちからの啓発が重要である。
d 登録販売者は、一般用医薬品の販売等に従事する医薬関係者(専門家)として、 適切なセルフメディケーションの普及定着、医薬品の適正使用の推進のため、啓発活動に積極的に参加、協力することが期待される。
a b c d
1 正 正 正 正
2 誤 正 正 正
3 正 誤 正 正
4 正 正 誤 正
5 正 正 正 誤
問60
a.正
b.正
c.正
d.正
正答:1
他の問題・解説はこちらへ→ 一 覧


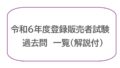
コメント